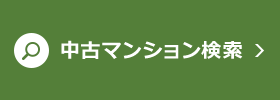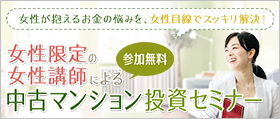物価上昇が取りざたされている昨今、都心部のマンション賃料にも上昇傾向が見られます。
今回は賃料上昇から不動産投資を解説していきたいと思います。
2025年5月、不動産情報を発信しているアットホームは、東京23区の30㎡以下の単身者向けマンションの平均賃料が10万円を突破したと発表しました。これは前年同月比で+8.4%という大幅な上昇であり、12ヶ月連続で高値を更新し続けています。
前年同月比上昇率トップ3は、1位【千葉県】+8.8%(70,879円)2位【福岡市】+8.7%(57,269円)3位【東京23区】+8.4%(100,634円)という結果です。(引用:アットホーム)
賃料上昇の背景
- 賃貸物件の需要増加…コロナ禍以降、本格的な経済活動の再開によって、都市部には人口流入が増加しており、その結果、単身向けマンションの需要がさらに増加して、賃料上昇に繫がっている。
- 供給減少…資材や人件費の高騰による建築コスト増や都市部における開発用地の減少によって、単身向けマンションの新築供給は減少しています。また晩婚化で平均入居年数が長くなり、既存物件に空室が出にくくなったことも影響しています。
- 住宅購入を諦めて、賃貸に移行する人が増えている。昨今の住宅価格の高騰により購入を諦めた層が増えたことで、賃貸需要が高まっているという事情が伺えます。
賃料が上昇しやすい立地とは
賃貸需要が高く、かつ新築物件の供給が少ない立地であれば、賃料が安定しており、上昇期待も持てる立地と言えます。これは需要と供給のバランスですが、住みたい人が沢山いる立地では、賃貸人気があるので賃料を下げる必要もなく、新築物件の供給が少ない立地であれば、住みたい需要に対して供給も少ないので、賃料の安定化に繋がります。反対に住みたい人が少なくて(賃貸人気がない)、かつ新築物件の供給が多い立地だとすると、賃料は安定せずに下がってしまうリスクがあります。
不動産投資を検討する上で、賃料上昇に期待が持てるか、少なくとも賃料が下がるリスクが少ないかは、立地選びで左右されてきます。
賃貸需要が高い立地とは
商業施設やスーパー等の生活利便施設が充実している立地、駅からの近さや都心部へアクセスしやすい等の交通利便性が挙げられます。また、企業や大学が物件の近くにあるかどうかも、進学や就職によって生まれる賃貸需要を確保することに繋がります。
供給が少ない立地とは
新築物件を建設するためには、用地取得が必要となりますが、近年では都心部において土地取得が困難になってきています。例えば、弊社でも千代田区の新築物件は、2004年を最後に20年以上も新築物件の供給が出来ていません。山手線内側は日本政府の中枢や企業の本社が集中しており、大使館、教育機関や大型緑地、歴史的建造物や古くからの邸宅街などが数多く、土地の取得は容易ではありません。山手線内側の面積は東京都全体のわずか3%しかなく、希少性の高いことが言えるかと思います。また、最寄り駅からの徒歩分数も一つの目安になります。駅からの距離が遠ければ、マンションを建てられる土地は多くなり、距離が短くなれば土地が少なくなりますので、競合する物件も少なくなります。例えば、地方になると土地があるため、アパートとも競合してしまい、家賃の下落リスクにも繋がります。
投資物件をどのエリアで持つかも重要なポイントです。
先に挙げた、賃料上昇率トップ3の千葉県(70,879円)と東京23区(100,634円)を比較すると上昇率こそ千葉県が上回りますが、その賃料差は約3万円にもなります。マンション経営をする上で、管理費や修繕コスト等のランニングコストは、どこで物件を所有しても大きくは変わりませんが、取れる賃料には大きく差がありますし、立地によっては、家賃の下落リスクも高くなります。また、売却の出口戦略を考えた場合、家賃が下がってしまうとその分売却価格も下落してしまうリスクにも繋がります。
まとめ
弊社クレアスパートナーズでは、都心部の中古物件を多数取り扱っております。また、営業担当が賃貸会社と連携をして、更新時や入居者入れ替え時に賃料増額の相談にも臨機応変にご対応しております。少しでもご興味・ご関心お持ち頂いた方はお気軽にお問い合わせください。